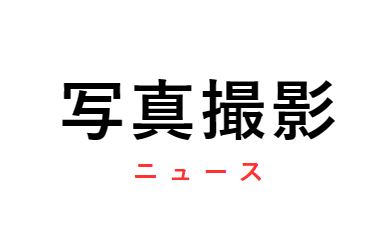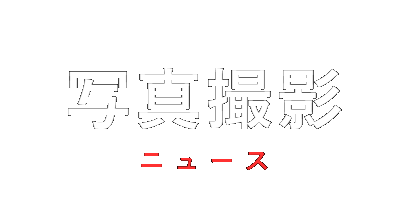2人の出会い
魚住誠一と常盤響の最初の出会いは、ポートレート専科の会場でのことでした。共通の友人を介して、魚住が主催する写真展について話を聞き、興味を持った常盤は展示を見に行きました。しかし、互いの顔を知らなかったため、初めは挨拶もままならなかったそうです。後に友人を通じて常盤が訪れていたことを知り、魚住は驚いたと言います。その後、第2回の展示を企画する際に、魚住は常盤に参加を依頼しました。異なるバックグラウンドを持つ4人のカメラマンが集まり、新たな化学反応を期待していました。
デザイナーからカメラマンへ
常盤響はもともとCDジャケットや映画のポスターのデザインを手掛けていましたが、1997年にブックデザインの仕事を受けたことがきっかけでカメラマンに転身しました。その仕事は阿部和重の「インディヴィジュアル・プロジェクション」という小説の表紙で、写真を使うことに強い魅力を感じたと言います。しかし、出版社の予算の都合上、自らが写真を撮ることになりました。その経験がきっかけで、写真による表現にのめり込んでいったそうです。
写真への情熱
魚住と常盤は、写真を通じて独自の世界観を表現しています。魚住は、異なるバックグラウンドを持つ人々が集まることで新しいアイデアや作品が生まれると信じており、常盤はデザイナーとしての経験を生かし、写真に独自の視点を加えています。二人の出会いは、写真という共通の言語を介して、互いのクリエイティブな旅を豊かにしています。
この記事は、常盤響と魚住誠一の出会いと、彼らが写真を通じてどのようにして自己表現を追求しているかに焦点を当てています。写真芸術に興味のある方にとって、彼らの話は大きな刺激となるでしょう。